
「産学連携」で未来へ加速
産学連携は企業と大学が共同で研究・開発を行い、新たな知識や技術を創出する取り組みとして近年ますます重要性を増しています。
この取り組みは、企業が持つ実行力と大学が保有する先進的な研究成果を結び付け、新しい製品やサービスの開発、さらには社会課題の解決へと繋がる可能性を秘めています。
ダイキン工業は国立大学法人東京科学大学(旧東京工業大学)と空調機のコア技術の高度化に向け、協働研究拠点を2024年9月に立ち上げました。

今回は、東京科学大学との産学連携を担当しているダイキンテクノロジーイノベーションセンター(以下TIC)小林直人技術戦略担当部長へのインタビューを通して
産学連携で共同研究の内容と今後の進め方、その先の展望についてご紹介いたします。
▶お話を伺った方

小林 直人
ダイキン工業株式会社
テクノロジー・イノベーションセンター テクノロジー・イノベーション戦略室技術戦略担当部長
ダイキン滋賀製作所で電気技術者としてモータやインバータの研究・開発を行う。
TIC設立にともない、TICインバータ技術グループへ異動。
2018年より東京大学との産学連携に携わり、2019年より東京大学駐在となる。
現在は、東京支社にて関東の大学を中心に産学連携のテーマ作りを行っている。
東京科学大学×ダイキン
空気だより:“東京科学大学“と産学連携にいたった経緯や目的を教えてください。
小林さん:東京科学大学はパワーエレクトロニクスで強みをもち、大学OBがダイキンのモータ・インバータの研究開発を主導したことで同大学とは古くからご縁がありました。東京科学大学には国際的な学会IEEE(アイ・トリプル・イー、Institute of Electrical and Electronics Engineering)のニコラ・テスラ賞を受賞している千葉明先生が在籍されており、協働研究拠点の立ち上げにご尽力いただきました。
未来のターボ圧縮機に関しての研究も行っており、共著で論文も出しております。
ベアリングレスモータのスラスト支持用零相電流が半径方向支持力に及ぼす影響の検討 | 文献情報 | J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター (jst.go.jp)
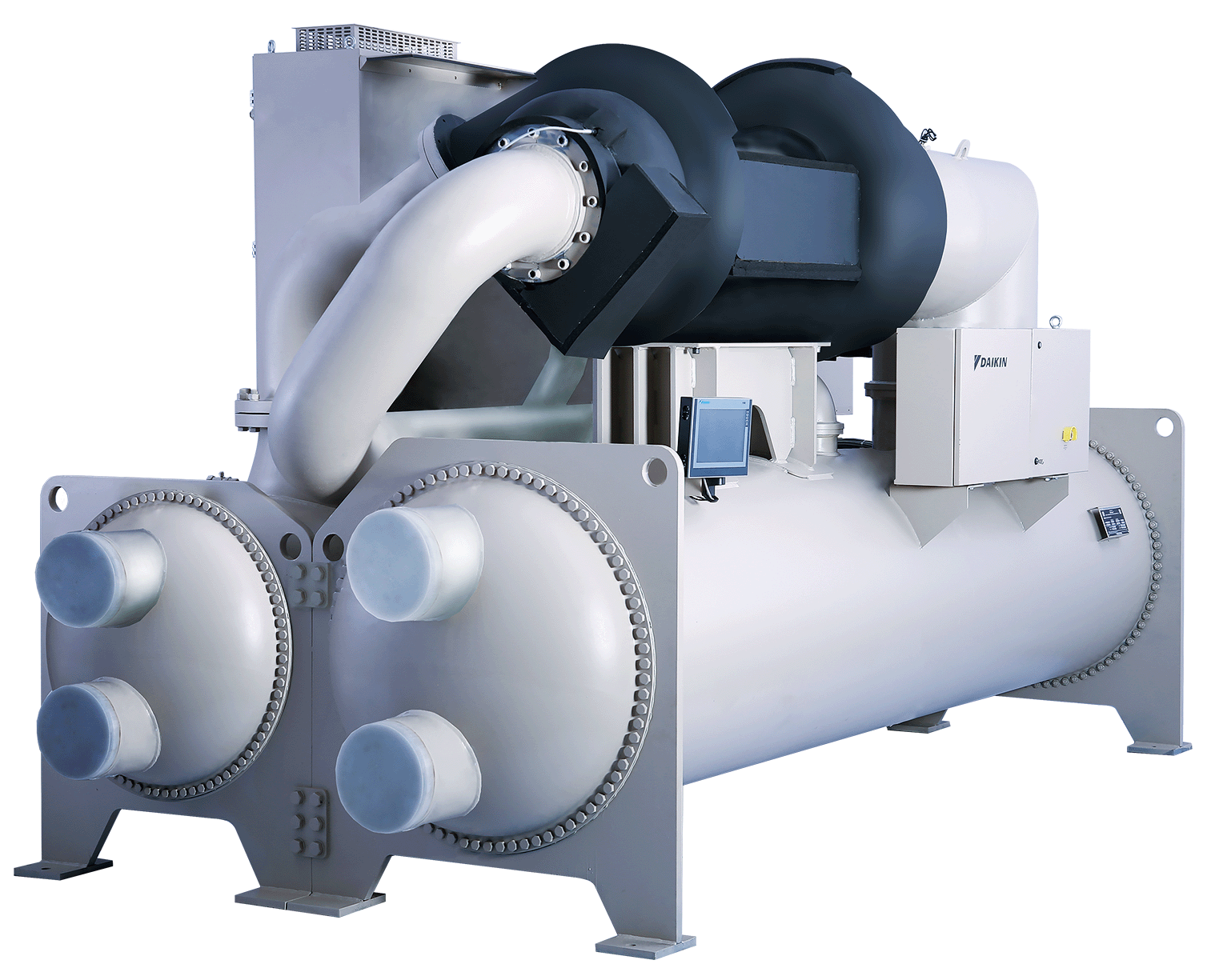
また、東京科学大学は、スーパーコンピュータ「TSUBAME」を所有しており、学内のみに限らず学外の研究機関・民間企業などに幅広く使われております。そこで、
① TSUBAMEを活用した圧縮機の解析・シミュレーション
② 高効率なモータ・インバータの研究
この二本柱を研究目的とおいています。
また、東京科学大学生自身が学んでいる機械技術・電気技術が、我々の空調コア技術に活かせるということを、共同研究を通じて知ってもらいたいという想いもあります。
空気だより:現在確定している研究内容はありますか?
小林さん:圧縮機開発のDXを実現するためスーパーコンピュータ「TSUBAME」を用いて圧縮機内部で起こっている様々な現象の解明について研究を行う予定です。また、モータ・インバータについてはこれまでにない新形式の提案を狙っています。今後4月以降にはもっと具体的なお話ができると思います。
空気だより:産学連携の東京科学大学とダイキン双方のメリットは何だと思われますか?
小林さん:ダイキンのメリットとしては、社内でも技術開発をしていますが、先進的な大学研究と連携することで従来には無い新しい発想を取り込んで、抱えている技術課題を全く新しいアプローチで解決が出来ることです。
東京科学大学のメリットは、研究内容を実際の製品に社会実装することで新しい研究課題を得ること、さらには、社会へむけて成果・実績を公開することで、研究への理解を広められることだと思います。
様々な課題が生まれ、技術革新のスピードが早い昨今、一つのゴールに対して色々な方法でのアプローチをともに導き出す産学連携はこれからの産業界ではより盛んになると思われます。
空調機は機械、電気、化学などの要素が関わる複合体です。冷媒を扱うには大掛かりな設備が必要であり、そのノウハウはダイキン固有のものです。今回、東京科学大学の機械・電気の先端研究成果とダイキンの空調機の知見を合わせることで、共同での実地試験を通じ、新しい空調機の市場投入を早めることを目指しています。
空気だより:今後の共同研究の進め方は?
小林さん:共同研究自体は2029年までの5年間を区切りとして、その時点で次年度以降について共同研究自体の継続の有無、テーマや内容の見直し等が行われる予定です。
空気だより:2029年には成果をダイキンとして出していかないといけないと思いますが、現状の懸念はありますか?
小林さん:研究は半年、1年では成果が出るものではなく、長くかかります。ただし、長くやっているだけになってしまい、最後、何も実現しないまま終わってしまうことを危惧しています。短い期間、例えば3か月、半年、1年ごとにプロジェクトの進捗に応じて、場合によってはテーマの見直し、改変などをきめ細やかにやっていく事が大切です。なんとなく1年、3年、5年とならないように、マイルストーンをしっかり定め、成果に繋げていきたいと思います。
▶編集後記
産学連携の話は、ニュースで聞くだけでどこか遠い世界の話だと思っていましたが、
インタビューを通じ、産学連携を行うことで技術革新による既存空調機器には無い新しい概念に繋がりそうな未来を感じることができました。
次回はダイキンコンタクトセンターの取り組みをご紹介します。
楽しみにして頂ければと思います!
▶関連リンク
・ダイキンの空気の技術 | ダイキン工業株式会社
・ダイキンと東京工業大学が「ダイキン空調技術協働研究拠点」を設置| ニュースリリース | ・空気だより 過去記事
「東京大学×ダイキン」前編 後編